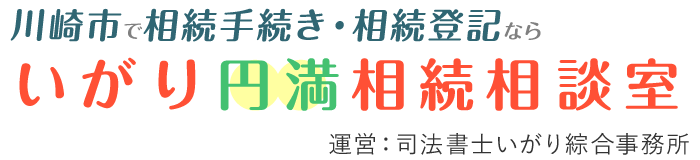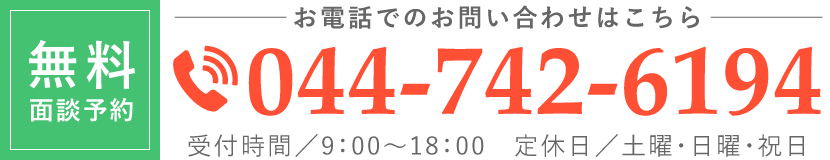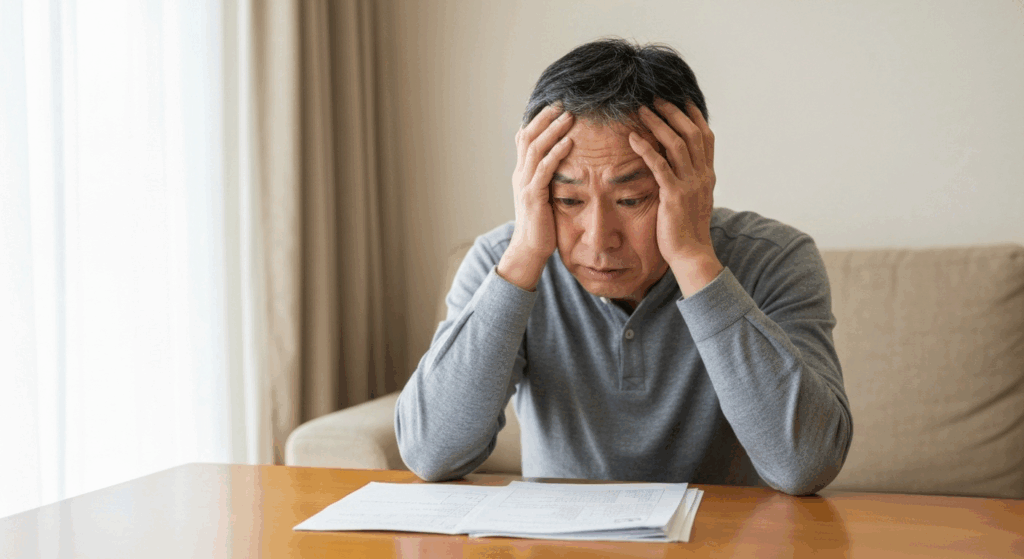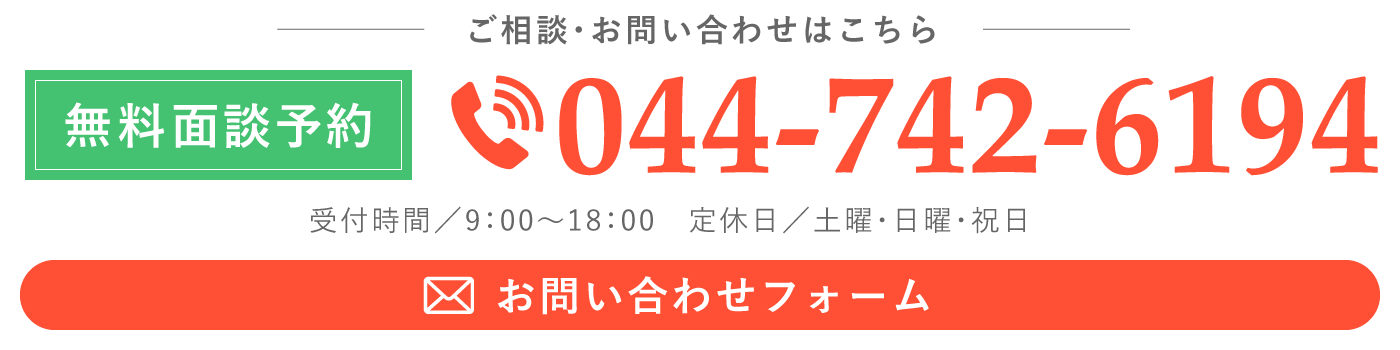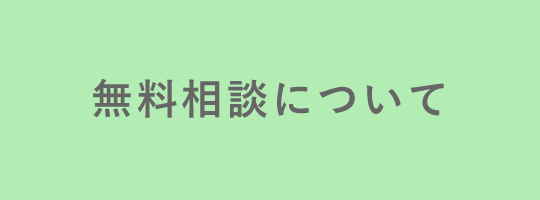このページの目次
「通帳がない…」後見制度を諦める前にご相談ください
「遠方の実家に住む母が認知症になってしまって…。施設の担当者から成年後見制度の利用を勧められたのですが、手続きを進められずに困っているんです」
先日、当事務所では、このような切実なご相談をいただきました。
詳しくお話を伺うと、お母様の預金通帳が実家で見当たらず、どうやら行方不明になっているお兄様が持ち出してしまった可能性が高いとのこと。銀行に相談しても「ご本人でないと再発行はできません。認知症であれば口座を凍結することになります」と突き放されてしまい、途方に暮れていらっしゃいました。
「後見の申立てには通帳のコピーや財産目録が必要と聞きましたが、肝心の通帳がないので財産も収支も全く分かりません。もう、後見制度の利用は諦めるしかないのでしょうか…?」
もし、あなたがこれと似た状況で頭を抱えているなら、どうかご安心ください。結論から申し上げますと、財産状況が完全にわからなくても、成年後見制度の申立ては可能です。
通帳が全くないというのは珍しいケースかもしれませんが、長年記帳されておらず入出金が不明な場合など、当事務所では同じように財産状況が不透明な案件での申立てを数多くサポートしてまいりました。
このようなケースでは、私たちが「詳細は後見人として選任された後、正式な権限で調査します」という内容の上申書を作成し、家庭裁判所に事情を説明します。
そもそも成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった方の権利と財産を守るための制度です。むしろ、今回のご相談のような状況こそ、後見人がご本人に代わって財産状況をきちんと調査し、明らかにするべきなのです。
ですから、書類が揃わないからといって、決して諦めないでください。
書類不足で手続きを放置する3つの深刻なリスク
「書類が揃うまで待とう」「もう少し様子を見よう」と手続きを先延ばしにすることで、取り返しのつかない事態を招いてしまう可能性があります。ここでは、専門家の視点から、手続きを放置した場合に起こりうる3つの深刻なリスクについて解説します。

リスク1:突然の口座凍結で生活費や介護費が引き出せない
ご家族が銀行窓口で「母が認知症で…」といった話をした途端、口座が凍結されてしまうケースは少なくありません。これは、銀行がご本人の財産を守るために行う正当な対応です。
しかし、一度凍結されてしまうと、たとえご家族であっても預金の引き出しは一切できなくなります。年金が振り込まれても、それを介護施設の費用や医療費、日々の生活費の支払いに充てることができません。結果として、ご家族が一時的に費用を立て替えなければならなくなり、経済的にも精神的にも大きな負担を強いられることになります。
リスク2:財産の全容が不明なまま散逸・横領される
ご本人の判断能力が低下すると、どこにどのような財産(預貯金、不動産、有価書証券など)があるのか、ご自身でも分からなくなってしまうことがあります。
財産の全容が不明なまま放置していると、知らぬ間に誰かが勝手に預金を引き出したり、不動産を売却してしまったりする危険性があります。特に、悪意のある第三者や、お金に困っている他の親族などが関わっている場合、財産が横領されてしまうリスクは決して低くありません。後からその事実が発覚しても、一度失われた財産を取り戻すことは極めて困難です。
リスク3:詐欺被害や不要な契約で財産が失われる
判断能力が低下した高齢者は、悪質な訪問販売や詐欺のターゲットにされやすいという悲しい現実があります。
次々と不要な高額商品を契約させられたり、巧妙な手口で多額のお金をだまし取られたりする被害が後を絶ちません。成年後見人が選任された場合、成年被後見人がした不利な契約について取り消しや無効主張が可能となる場合があります。ただし、契約の内容や相手方の状況などにより個別の法的検討が必要です。手続きをしなければ、そうした法的な保護を受けることができず、大切な財産が一方的に失われてしまうのです。
結論:書類がなくても後見申立ては可能です
前章で述べたようなリスクを回避するためにも、一刻も早く手続きを進めることが重要です。そして、この記事で最もお伝えしたいことは、たとえ通帳などの書類が手元になくても、成年後見の申立てはできるということです。
「完璧な書類を揃えなければならない」と思い込んでいる方が多くいらっしゃいますが、それは誤解です。家庭裁判所も、申立ての段階ですべての財産を正確に把握することが難しいケースがあることは理解しています。
財産目録は「申立て時点で判明している範囲」で作成する
申立ての際に提出する「財産目録」は、あくまで申立人(ご家族など)がその時点で把握している範囲で作成すれば問題ありません。例えば、
- 手元にある古い通帳のコピー
- 固定資産税の納税通知書
- 年金の振込通知書
といった断片的な情報から、わかる範囲で記載します。もし情報が何もない場合でも、その旨を正直に申告すれば、家庭裁判所は事情を汲んでくれます。完璧な財産目録を作成することよりも、まずは申立てを行い、ご本人を法的な保護下に置くことが最優先されるのです。
詳細な財産調査は後見人の正式な権限で行う
申立てが受理され、家庭裁判所によって成年後見人が選任されると、状況は大きく変わります。成年後見人は、ご本人の「法的な代理人」として、強力な調査権限を持つからです。
後見人はその権限に基づき、各金融機関に預金残高の照会を行ったり、市区町村役場で不動産の評価証明書を取得したりと、正々堂々と財産調査を進めることができます。ご家族では「本人でないと…」と断られてしまった手続きも、後見人であれば、裁判所の審判書謄本などを用いて金融機関等への照会や手続きを進めやすくなります。
このように、個人では調査が困難な状況でも、後見制度を利用すれば、ご本人の財産の全容を正確に把握し、適切に管理していく道が開けます。

後見開始申立ての必要書類と収集のポイント
では、具体的にどのような書類が必要になるのでしょうか。ここでは、家庭裁判所が一般的に求める書類を分類し、収集する際のポイントを専門家の視点から解説します。ただし、事案によっては追加の書類が必要になる場合もあります。
本人や申立人に関する書類
ご本人や申立てをするご家族を特定し、関係性を証明するための基本的な書類です。
- 戸籍謄本(本人):本籍地の市区町村役場で取得します。
- 住民票(本人・後見人候補者):住所地の市区町村役場で取得します。
- 登記されていないことの証明書(本人):成年後見制度をまだ利用していないことを証明する書類です。全国の法務局・地方法務局の本局で取得できます。郵送での請求も可能です。
- 申立書、申立事情説明書、親族関係図など:裁判所のウェブサイトで書式をダウンロードし、作成します。
これらの書類の多くは、発行から3ヶ月以内といった有効期限が定められているため、計画的に収集する必要があります。
本人の判断能力に関する書類
後見制度を開始する必要があるかどうかを、医学的な見地から証明するための極めて重要な書類です。
- 医師の診断書:後見申立てで最も重要な書類の一つです。かかりつけ医に作成を依頼するのが一般的ですが、精神科や心療内科、物忘れ外来などの専門医に診察を受けて作成してもらう方がスムーズな場合もあります。診断書の書式は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできますので、事前に医師にお渡しするとよいでしょう。

財産・収支に関する書類(わかる範囲で準備)
この記事のテーマである、財産や収支に関する書類です。繰り返しになりますが、あくまで「わかる範囲」「手元にあるもの」で構いません。
- 財産目録:預貯金、不動産、有価証券、保険などを一覧にしたものです。
- 収支予定表:年金などの収入と、生活費や医療費などの支出をまとめたものです。
- 上記を裏付ける資料:
- 預貯金通帳のコピー、残高証明書
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書
- 保険証券のコピー
- 年金額がわかる通知書(年金振込通知書など)のコピー
これらの書類が一つも手元にない場合でも、決して諦める必要はありません。その状況を正直に裁判所に伝えることが大切です。
参考:後見開始(家庭裁判所ウェブサイト)——申立書、診断書、財産目録等が主要な必要書類として案内されています。詳細は上記リンク先にてご確認ください。
書類集めや申立ては専門家への依頼が確実な理由
ここまでお読みいただき、「思ったより手続きが複雑そう…」「自分ひとりでできるだろうか」と不安に感じた方もいらっしゃるかもしれません。そのような方のために、私たち司法書士のような専門家がいます。特に、書類が不足しているような難しいケースでは、専門家に依頼するメリットは非常に大きくなります。
当事務所の成年後見をご検討中の方へのページでも詳しくご案内しておりますが、専門家に依頼することで、以下のようなサポートが受けられます。
複雑な書類作成と収集をすべて代行
司法書士にご依頼いただくことで、戸籍謄本や住民票、不動産の登記事項証明書などを職務上の権限に基づき収集することが可能です。また、申立書や財産目録、申立事情説明書といった、作成に専門的な知識を要する書類も、ご本人やご家族から丁寧にお話を伺いながら、正確に作成します。これにより、皆様の煩雑な手続きにかかる時間と労力を大幅に削減できます。
裁判所への提出やその後のやり取りもスムーズ
私たちは、家庭裁判所がどのような点を重視して審理を進めるかを熟知しています。そのため、裁判所が求めるポイントを押さえた申立書類を作成でき、申立て後の裁判所からの問い合わせ(照会)にも的確に対応することが可能です。これにより、手続き全体がスムーズに進み、審理期間の短縮にも繋がる可能性があります。
書類がないケースでも最適な対応策を提案
まさに、この記事で取り上げたような「通帳がない」「財産の詳細が不明」といった困難なケースこそ、専門家の真価が発揮される場面です。私たちは、単に「書類がありません」で終わらせるのではなく、冒頭の事例のように「上申書」を作成して裁判所に事情を丁寧に説明したり、今後の調査計画を具体的に提示したりすることで、申立てが円滑に受理されるよう働きかけます。豊富な経験に基づき、それぞれの状況に応じた最適な対応策をご提案できるのが、当事務所の特徴です。
もし手続きでお困りでしたら、お気軽に後見制度に関するお問い合わせはこちらからご連絡ください。
まとめ:一人で悩まず、まずは専門家にご相談を
成年後見制度の申立ては、認知症などによって判断能力が不十分になった大切なご家族の権利と財産を守るための、非常に重要な手続きです。「必要書類が揃わないから」という理由で諦めてしまうと、ご本人が様々なリスクに晒され続けることになりかねません。
この記事でお伝えしたように、財産の詳細がわからなくても、手続きを進める方法は必ずあります。一人で抱え込まず、まずはその道のプロに相談してみませんか?
いがり綜合事務所(所在地:神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号、代表司法書士:猪狩 佳亮、所属:神奈川県司法書士会)は、成年後見に関するご相談を承っております。ご相談者様のお話を親身にお伺いし、不安な心に「安心」を届けられるよう、最善の解決策を一緒に考えさせていただきます。
お仕事でお忙しい方でもご相談いただきやすいよう、平日夜間や土日祝日のご相談にも対応(要事前予約)しております。初回のご相談は無料(60分程度・事務所での面談またはオンライン)ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。