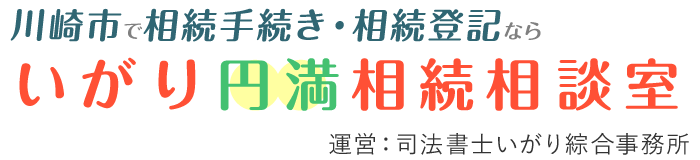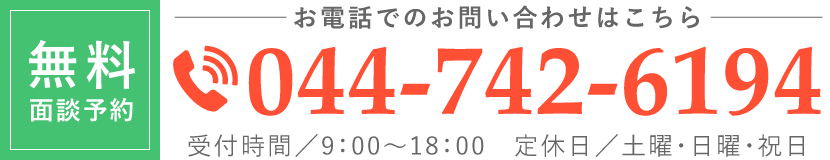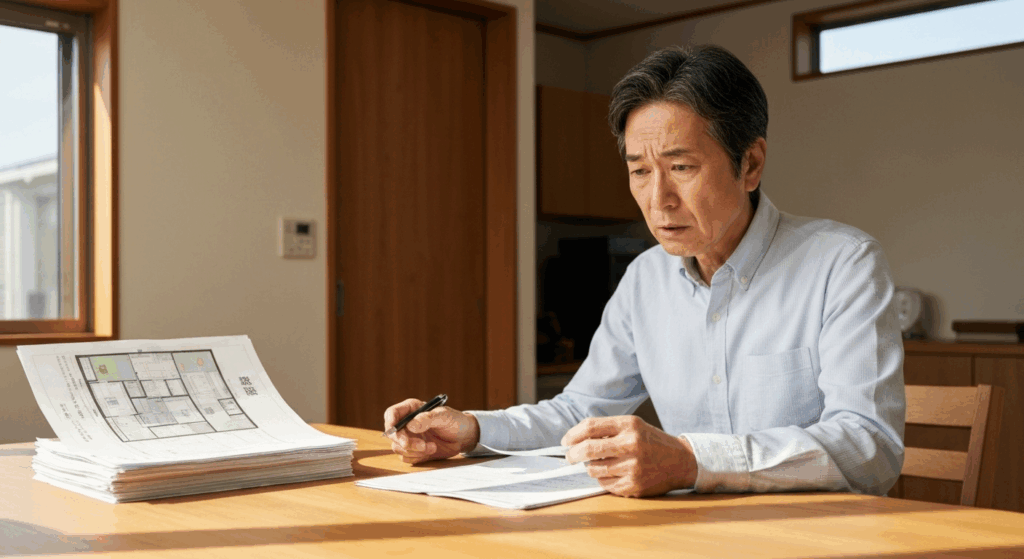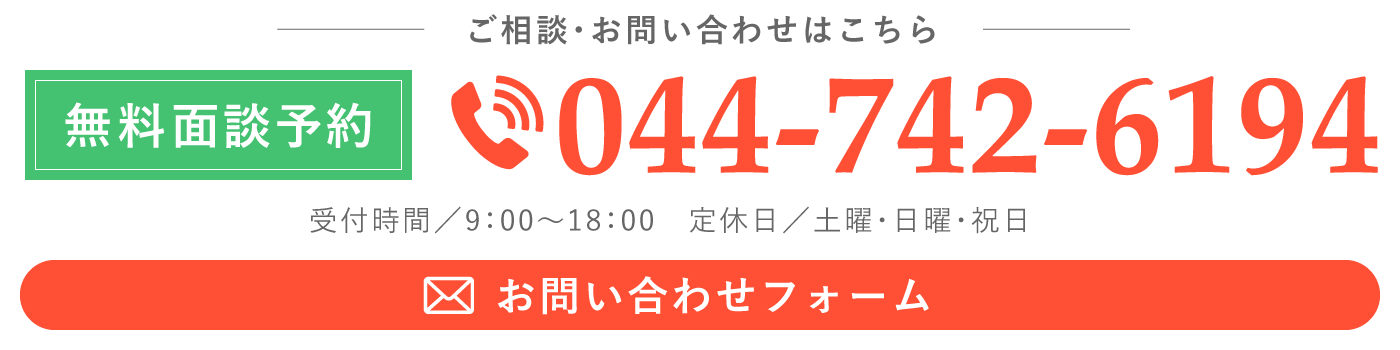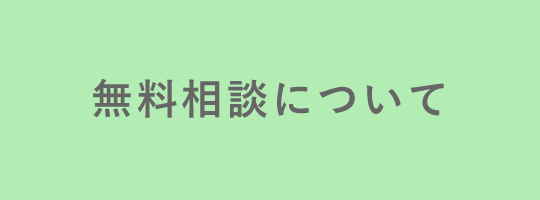このページの目次
「まさかうちも?」相続登記で私道を見落としていませんか?
「親から相続した実家を売却しようとしたら、不動産会社から『家の前の道路(私道)の登記が漏れていますね』と指摘された…」
「自分で頑張って相続登記を済ませたけれど、そういえば道路のことなんて考えたこともなかった。もしかして、うちも…?」
このようにお考えになり、ひやっとした経験はございませんか?
相続手続きの中でも、特に不動産の名義変更である「相続登記」は専門的な知識が必要です。特に、ご自宅の敷地だけでなく、それに接する「私道」の共有持分は、意外なほど見落とされがちな落とし穴なのです。
私道の登記漏れは、最初は小さな見落としかもしれません。しかし、それを放置してしまうと、後になって「不動産が売れない」「家が建て替えられない」といった深刻な事態を引き起こす可能性があります。さらに、一度終えたはずの遺産分割協議を、何年も経ってから相続人全員でやり直さなければならない…という、考えただけでも頭が痛くなるような面倒な手続きにつながることも少なくありません。
この記事では、川崎市で相続を専門的に扱う「いがり円満相続相談室」の司法書士の視点から、
- なぜ私道の相続登記は見落とされやすいのか
- 登記漏れを放置する深刻なリスク
- 専門家が行う私道の調査方法とその留意点
- 登記漏れが発覚した際の具体的な解決策
などを、分かりやすく解説していきます。今まさに不安を感じているあなたの心が少しでも軽くなり、「どうすれば良いか」という次の一歩を踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。
なぜ私道の相続登記は見落とされやすいのか?
「どうして気づかなかったんだろう…」とご自身を責めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。私道の相続登記漏れは、決して珍しいことではなく、誰にでも起こりうる問題です。それには、はっきりとした理由があります。
原因1:固定資産税が非課税なので通知書に載らない
私道の登記が見落とされる大きな原因の一つに、固定資産税が非課税となるケースがあることです。私道のうち、要件を満たして「公共の用に供する道路」と認められる場合は固定資産税が非課税となることがあり、この場合、課税明細に載らない私道が存在することになります。
地域住民の通行のために使われている「公衆用道路」とみなされる私道は、多くの場合、固定資産税が課税されません。そのため、毎年春ごろに市区町村から送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に同封されている課税明細書に、私道の情報が記載されないのです。
多くの方が、この課税明細書を見て相続不動産をリストアップするため、そこに記載のない私道の存在に気づくことができず、結果として相続登記から漏れてしまうのです。
原因2:「道路は共有財産」という思い込み
「家の前の道は、近所のみんなで使っている道路だ」という感覚も、見落としの一因です。
特に、複数の家で共有している私道の場合、それが個人の財産(正確には、不動産の一部を他の人と共有している「共有持分」という権利)であるという意識が薄れがちです。そのため、亡くなった方の財産として認識されず、相続人全員で財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」の議題にも上がらないまま、手続きが進んでしまうことがあります。
登記漏れを放置する深刻なリスク|売れない・建てられない!
「登記が漏れていても、今まで特に困らなかったし…」と軽く考えてしまうのは危険です。私道の相続登記漏れを放置すると、将来、ご自身の資産計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。

リスク1:不動産を売りたい時に売却できない
最も現実的なリスクが、不動産の売却時です。いざ実家を売却しようとしても、私道の共有持分の名義が亡くなった方のままでは、法的に所有権が買主に移転できません。
そのため、不動産会社や金融機関から私道の登記状況を理由に売却や融資手続きに制約がかかることがあります。結果として、売りたいタイミングで不動産を売却できなくなってしまうのです。
リスク2:家を建て替えられない(再建築不可)
建築基準法では、建物を建てる敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という「接道義務」が定められています。この「道路」には、当然ながら私道も含まれます。
もし、相続した土地が私道にしか接していない場合、その私道の共有持分を相続登記していなければ、法的には「道路に接していない土地」とみなされてしまう恐れがあります。そうなると、「再建築不可物件」となり、家の建て替えはもちろん、大規模なリフォームもできなくなる可能性があります。これは、不動産の資産価値を著しく下げる要因となります。
リスク3:時間が経つほど手続きが複雑化する
登記漏れを放置する期間が長引けば長引くほど、解決は困難を極めます。
例えば、10年前のお父様の相続で私道の登記が漏れていたとします。その後に、相続人の一人であったお母様が亡くなられた場合、どうなるでしょうか。この場合、当初の相続人(子など)だけでなく、お母様の相続人(子が複数いればその全員)も含めて、改めて遺産分割協議をしなければならなくなります。
さらに世代が進むと、甥や姪など、普段ほとんど交流のない親族まで手続きに巻き込む必要が出てきます。関係者がネズミ算式に増え、全員から実印をもらうだけでも大変な労力と精神的な負担がかかることになるのです。
相続財産に私道があるか?プロが行う調査方法とその留意点
「うちの場合は大丈夫だろうか?」とご心配な方のために、私たち司法書士が実際に行う調査方法のステップをご紹介します。ご自身で確認する際のヒントにもなりますが、正確な判断には専門知識が必要な場合も多いことをご理解ください。

ステップ1:手元の資料を確認する(権利証・売買契約書)
まずは、ご自宅に保管されている書類を確認してみましょう。特に重要なのが、亡くなった方が不動産を取得した際の「登記済権利証」(または「登記識別情報通知」)や「売買契約書」です。
これらの書類の「不動産の表示」という欄を注意深く見てください。ご自宅の土地(地目:宅地)のほかに、「所在」「地番」が異なり、「地目」が「公衆用道路」となっている土地や、「持分 〇分の〇」といった記載があれば、それが私道の共有持分である可能性が高いです。
ステップ2:役所で「名寄帳」を取得する
次に、不動産が所在する市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で「名寄帳(なよせちょう)」を取得します。名寄帳とは、その市区町村内において、ある特定の人が所有する不動産を一覧にしたものです。
ただし、ここで注意が必要です。前述の通り、固定資産税が非課税の私道はこの名寄帳に記載されていない場合があります。名寄帳は有力な手がかりですが、これだけで「私道はない」と断定するのは早計です。
ステップ3:法務局で「公図」と「登記事項証明書」を読み解く
最も確実な調査は、法務局での調査です。
まず「公図(こうず)」を取得し、ご自宅の土地がどのようになっているか、地図上で確認します。家の前の道路部分に地番が付されている場合、それは私道である可能性が高いです。公図から私道と思われる部分の地番を特定します。
次に、その地番の「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得します。この書類の「権利部(甲区)」を見れば、現在の所有者が誰で、共有の場合は誰がどのくらいの持分を持っているかが正確に分かります。ここに亡くなった方のお名前があれば、相続登記が必要な財産ということになります。なお、これらの書類は法務局の窓口のほか、オンラインでの取得も可能です。
【司法書士の現場】実際の私道調査事例
先日、戸建てのご実家を相続された方から相続登記のご依頼がありました。いつものように、まずはお客様からお預かりした固定資産税の課税明細書をもとに、相続する不動産(建物と敷地)を確認しました。
一見すると、これで全てのように思えます。しかし、私たちは必ず法務局で公図を取得して周辺状況を確認します。事務所に戻って公図を広げ、地形をじっくりと確認すると、どうもご自宅前の道路は私道ではないか、という疑念が浮かびました。
すぐさまその道路部分の地番を特定し、登記事項証明書を取得したところ、やはり、その道路は近隣の数軒の所有者で共有されている私道であり、亡くなったお父様も共有持分をお持ちであることが判明しました。
もし課税明細書だけの確認で手続きを進めていたら、この重要な私道は見落とされ、将来お客様が売却などで困ってしまうところでした。この事例のように、漏れなくすべての不動産を相続登記するには、課税明細書だけに頼らない、専門家による正確な調査が不可欠なのです。
私道の登記漏れが発覚!今からでも間に合う解決策
もし、ご自身のケースで私道の登記漏れが発覚したとしても、決して慌てる必要はありません。今からでも、正しい手順を踏めばきちんと解決できます。ここでは、その具体的なステップを解説します。

1. 相続人全員で再度「遺産分割協議」を行う
まず最初に行うべきことは、相続人全員で、登記が漏れていた私道について改めて話し合うことです。これを「遺産分割協議」と呼びます。
「この私道の持分は、誰が相続するのか」を決めます。一般的には、その私道に接しているご自宅の敷地を相続した方が、利便性を考えて私道の持分も合わせて相続するケースがほとんどです。
2. 私道に関する「遺産分割協議書」を作成する
相続人全員の話し合いがまとまったら、その内容を法的な効力のある書面、「遺産分割協議書」として作成します。
この書類には、登記事項証明書に記載されている通りに、私道の所在、地番、地目、地積、そして誰がどの持分を相続するのかを正確に記載する必要があります。そして、相続人全員が署名し、実印を押印します。この遺産分割協議書が、後の登記申請で重要な添付書類となります。
3. 法務局へ追加で相続登記を申請する
作成した遺産分割協議書と、その他必要となる戸籍謄本などを揃えて、管轄の法務局へ私道の共有持分に関する相続登記を申請します。申請が受理されれば名義変更が行われますが、書類不備や関係者の同意が得られない場合は追加の手続(戸籍の取得、相続人の特定など)が必要になることがあります。
これらの手続きは、書類の収集や作成に専門的な知識を要するため、ご自身で行うのは大変な労力がかかります。スムーズかつ確実に行うためには、司法書士にご依頼いただくのが一般的です。
私道だけじゃない!見落としやすい相続財産
実は、相続登記で見落とされやすい不動産は私道だけではありません。もう一つ、注意が必要なのがマンションの共用部分の土地です。
通常、マンションの部屋(専有部分)を所有していると、その敷地(土地)の権利も「敷地権」として一体化して登記されています。しかし、古いマンションなどでは、敷地とは別の土地に建てられた集会所、駐車場、ゴミ置き場などの土地の権利が、敷地権とは別に、各部屋の所有者で共有しているケースがあります。
これも私道と同様、固定資産税が課税されていなかったり、権利を持っているという意識が薄かったりするため、登記から漏れやすい財産です。心当たりのある方は、一度確認してみることをお勧めします。

不安なままにせず、まずは専門家にご相談ください
ここまでお読みいただき、相続財産に私道が含まれているかの調査や、登記漏れが発覚した場合の手続きは、ご自身で完璧に行うのがいかに難しいかを感じていただけたかと思います。公図や登記事項証明書を正確に読み解き、法的に有効な書類を作成するには、やはり専門的な知識と経験が不可欠です。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない場合には10万円以下の過料が科される可能性があると定められています。私道の登記漏れも、この義務化の対象となります。
「もしかしたらうちも…」という不安を抱えたまま、一人で悩んでいても問題は解決しません。そのような時こそ、私たち相続の専門家である司法書士を頼ってください。
司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所では、お客様一人ひとりのお話にじっくりと耳を傾け、何が最善の解決策なのかを一緒に考えさせていただきます。初回のご相談は無料ですので、どうぞ安心して、現在の状況をお聞かせください。専門家へのご相談が、あなたの不安を解消し、問題を解決する一助となる可能性があります。
—
司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所
代表 司法書士 猪狩 佳亮(神奈川県司法書士会所属)
〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12番14号 シャンボール川崎505号

司法書士・行政書士・社会保険労務士いがり綜合事務所の司法書士 猪狩 佳亮(いがり よしあき)です。神奈川県川崎市で生まれ育ち、現在は遺言や相続のご相談を中心に、地域の皆さまの安心につながるお手伝いをしています。8年の会社員経験を経て司法書士となり、これまで年間100件を超える相続案件に対応。実務書の執筆や研修の講師としても活動しています。どんなご相談も丁寧に伺いますので、気軽にお声がけください。